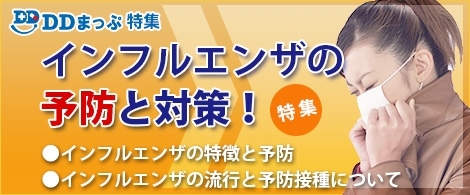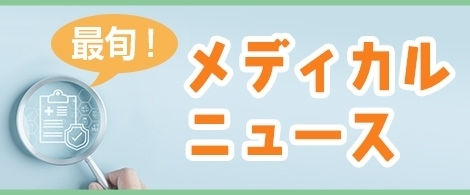DDまっぷは全国の病院・診療所・歯科を検索できる病院検索サイトです。
マイコプラズマ肺炎とは?症状や薬、予防法について解説
季節の変わり目や特定の時期になると、子どもの間で流行する「しつこい咳」。ただの風邪だと思っていたら、実は「マイコプラズマ肺炎」かもしれません。
この記事では、マイコプラズマ肺炎とはどのような病気なのか、その特徴的な症状や検査と診断、そして治療法や登園・登校の基準に至るまで詳しく解説します。
マイコプラズマ肺炎とは

マイコプラズマ肺炎は「肺炎マイコプラズマ(Mycoplasma pneumoniae)」と呼ばれる細菌に感染することで引き起こされる呼吸器感染症です。この菌は、生物学的に細菌とウイルスの間に位置づけられ、細胞壁を持たないという特徴があります。このため、一般的な細菌に効果のある、細胞壁合成阻害剤のペニシリン系・セフェム系の抗菌薬(抗生物質)が効きにくいという性質を持っています。[1]
感染経路は、患者の咳のしぶきに含まれる病原体を吸い込むことによる「飛沫感染」と、病原体が付着した手で口や鼻に触れることによる「接触感染」が主です。年間を通じて感染が報告されますが、特に秋から冬にかけて流行のピークを迎える傾向があります。幼児期から学童期の子どもに多く見られますが、大人が感染することもあり、家庭内や学校などの閉鎖的な環境で感染が広がりやすい疾患です。[2]
マイコプラズマ肺炎の症状
マイコプラズマ肺炎は、発熱、全身倦怠感、頭痛といった前駆症状に続き、発症後3?5日目頃から乾性咳嗽、つまり痰を伴わない空咳が出現するのが典型的です。この咳嗽は頑固で、解熱後も3?4週間と長く続く傾向があり、経過中に痰が絡む湿性咳嗽へと変化していくこともあります。
一般に軽症で済む場合が多いですが、時に重症化したり、中耳炎や胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を引き起こしたりするリスクもあるため、注意が必要です。[3]
マイコプラズマ肺炎の潜伏期間
潜伏期間とは感染してから症状が現れるまでの期間を指します。
一般的な風邪やインフルエンザが1?3日であるのに対し、マイコプラズマ肺炎は通常2?3週間と比較的長いのが特徴です。[3]
このため、感染源を特定しにくく、気づかないうちに家庭内や学校などで感染が拡大する一因となっています。
マイコプラズマ肺炎の検査と診断
マイコプラズマ肺炎は、周囲での流行状況や症状の経過から診断される場合もありますが、正確な診断のために検査が行われることもあります。主な検査方法は以下のとおりです。[4][5]
- 血液検査(抗体検査):
- マイコプラズマに対する抗体価を測定します。感染初期には抗体が十分上昇していない場合もあり、確定診断には発症後と一定期間後のペア血清で抗体価の変化を確認する必要があります。ただし結果が出るまでに数日間かかるため、即日の診断には適しません。
- 迅速抗原検査:
- のどの粘膜を綿棒で採取し肺炎マイコプラズマの抗原を検出します。検査時間はおよそ15~30分程度で結果が出ますが、感度(正確さ)が高くないため、実際に感染していても陰性になる(見逃す)ことがあります。
- 核酸増幅法(遺伝子検査):
- マイコプラズマのDNA/RNAを検出する方法で、例としてLAMP法やQプローブ法があります。病原体の遺伝子を直接検出するため最も精度が高い検査法ですが、特殊な機器を要するため全ての医療機関で実施できるわけではありません。
マイコプラズマ肺炎の登園・登校基準
子どもがマイコプラズマ肺炎と診断された場合、いつから登園・登校してよいのかは保護者にとって大きな関心事です。
マイコプラズマ肺炎は、学校保健安全法で「その他の感染症」に分類されており、明確な出席停止期間が定められていません。そのため、登園・登校を再開する目安は、医師が感染の恐れがないと判断した場合となります。[6]
一般的には、「解熱し、激しい咳が治まり、普段通りの食事がとれるようになってから」がひとつの目安とされていますが、最終的な判断は主治医の指示に従うようにしてください。
マイコプラズマ肺炎の治療薬

マイコプラズマ肺炎の治療では、有効な抗菌薬の投与と、発熱や咳に対する対症療法が基本となります。高熱の場合は解熱剤の使用、咳が辛い場合は鎮咳薬や去痰薬の処方など、症状に応じた薬が用いられます。
また、抗菌薬の第一選択はマクロライド系抗菌薬です。具体的にはクラリスロマイシンやアジスロマイシンといった薬剤がよく使われ、これらは肺炎マイコプラズマのタンパク質合成を阻害し、高い抗菌効果を示します。
マイコプラズマ肺炎の耐性菌問題
近年一部の肺炎マイコプラズマはマクロライド系薬が効きにくい耐性菌(マクロライド耐性菌)になっており、問題となっています。
日本では2000年代にマクロライド耐性菌が急増し、2012年には耐性率が80%に達しましたが、その後一時低下し約20~30%程度になりました。しかし2024年には再び増加傾向が報告され、2016~2017年以来の約60%の耐性率が報告されています。[1]
このように耐性菌の存在があるため、抗菌薬は乱用せず適切に使用することが大切です。
マクロライド系で治療しても効果が乏しく、マクロライド耐性マイコプラズマ肺炎が疑われる場合には、別の種類の抗菌薬に切り替えることがあります。
具体的には、小児でも使用可能なニューキノロン系抗菌薬のトスフロキサシン(新しいキノロン系)や、テトラサイクリン系抗菌薬のミノサイクリンなどが選択肢となります。ただし、テトラサイクリン系の薬は小さい子どもでは歯牙着色のリスクがあるため、一般には8歳以上の年長児や成人に限定して用いられることが多い点に注意が必要です。
どの薬を使うかの判断は患者の年齢や症状の重さによって異なりますので、担当医の指示に従ってください。[1][7]
マイコプラズマ肺炎の予防法
現在、マイコプラズマ肺炎に対して有効なワクチンはありません。したがって、予防には一般的な感染対策を徹底することが最も重要となります。
具体的には、流水と石鹸によるこまめな手洗いを行い、流行時期には人混みを避けてマスクを着用することも有効な対策となります。
家庭内や学校など、集団生活の場では、定期的な換気も重要です。もし家族が感染した場合は、食器やタオルの共用は避けましょう。[2]
長引く咳が気になる場合には早めに医療機関を受診しよう!
マイコプラズマ肺炎は、秋から冬にかけて流行のピークが見られる呼吸器感染症です。
長引く咳や発熱などの気になる症状がみられる場合は、自己判断で市販の風邪薬を飲み続けたりせず、早めに受診しましょう。医療機関は子どもの場合は小児科、大人の場合は一般内科・呼吸器内科を受診すると良いでしょう。
【監修】
株式会社Officeファーマヘルス
【参考文献】
[1]大石智洋,小児におけるマイコプラズマ感染症の現況,診断と新薬2024,61.473-479
[3]東京都感染症情報センター マイコプラズマ肺炎ってどんな病気?
[4]国立研究開発法人 国立成育医療研究センター マイコプラズマ肺炎